国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯を対象に5年ごとに実施する、暮らしの設計図づくりのための最も基本的な統計です。医療・保育・防災・交通から選挙区まで幅広く活用され、回答は法に基づく義務。10月1日時点の状況を、オンラインや紙で簡単に回答できます。個人情報は厳格に保護され目的外利用はありません。公式連絡と調査員の見分け方や詐欺対策も解説します。基準日は毎回10月1日。常住地の考え方や引っ越し・留学など迷いやすいケース、期限後の提出方法、ID再発行、アクセシビリティや多言語対応、偽サイトの見抜き方まで、安心して回答いただくためのポイントをまとめました。皆さまの一回答が地域の未来を支えます。
- 国勢調査とは何で、私たちの暮らしにどんな意味があるの?
- 調査は誰が対象で、いつ・どのような方法で実施されるの?
- 回答は義務なの?期限や回答方法(オンライン・紙・訪問)はどうなっているの?
- 個人情報とプライバシーはどのように守られ、結果は何に活用されるの?
- 個人情報とプライバシーを守る基本原則
- 現場での安全対策—紙とオンラインの両面
- よくある心配への答え
- 集計結果はどこで見られ、どう役立つのか
- 統計づくりの舞台裏—データはこうして安全に加工される
- 安心して参加するためのワンポイント
- あなたの一回答が、安心で便利な社会をつくる
- 正しい国勢調査を見分けるには?公式連絡や調査員の確認方法・詐欺の見抜き方は?
- 公式な案内・書類の見方
- 調査員が訪ねてきたときのチェックリスト
- インターネット回答を装う偽サイトへの対策
- 典型的な手口と即断ポイント
- 紙の調査票を安全に扱うコツ
- 「怪しい」と感じたら—安全第一の行動手順
- 住まいの状況に応じた注意点
- ワンチェックで安心—本物かどうかの合言葉
- 地域でできる見守りと周知
- 安心して回答するために
- 最後に
国勢調査とは何で、私たちの暮らしにどんな意味があるの?
国勢調査とは——日本の「いま」を映す、最も基本的な統計
国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯の実態を明らかにする、我が国最大規模の統計調査です。
大正9年(1920年)に始まり、5年ごとに実施されています。
調査の基準となる日は毎回同じで、10月1日現在の状況を把握します。
対象は国籍を問わず、日本で日常生活を送っているすべての方と世帯です。
性別・年齢・就業の状況・世帯構成・住宅の状況など、暮らしに関わる基礎的な項目を全国一斉かつ同じ基準で把握するため、地域間や時系列で正確に比較できることが大きな特長です。
国勢調査で得られたデータは「基幹統計」として、国や自治体の政策づくり、企業や研究機関の分析、地域コミュニティの活動に至るまで、幅広い意思決定の土台になります。
100年以上にわたり継続して蓄積されたデータは、日本社会の姿と変化を客観的に映し出す“社会の鏡”といえます。
国勢調査が私たちの暮らしに直結する理由
国勢調査の結果は、普段の生活のさまざまな場面で活用されています。
ここでは代表的な活用例を、身近な場面に即してご紹介します。
1. 災害に強い地域づくりの基盤
地震や台風などの災害対策では、地域ごとの人口構成(高齢者や子どもの人数、ひとり親世帯の数など)や住宅の種類、日中と夜間の人口の違いが重要な判断材料になります。
国勢調査はこうした情報を町丁・字単位など細かな地域区分で把握できるため、避難所の配置、備蓄物資の数量、要配慮者支援の動線設計など、現場で機能する計画づくりに欠かせません。
2. 子育て・教育の計画に直結
保育所やこども園、小中学校の設置・統廃合、学級数の見通しには、地域の年齢別人口の正確な把握が不可欠です。
今後数年間で何歳の子どもがどれくらい在住するかという見込みを立てる“基準の数字”として、国勢調査は使われます。
これにより、保育の待機や学級の過密を抑える、先手の投資が可能になります。
3. 医療・介護の体制づくりを支える
高齢化の進行度や単身高齢世帯の増減、通勤・通学の流れなどは、医療・介護の需要を左右します。
国勢調査のデータは、地域医療構想や介護保険事業計画の土台となり、病院や診療所の機能分担、訪問介護の提供体制、夜間・休日の救急体制の見直しに活かされます。
必要なときに必要なサービスが届く安心の基盤を、データで支えています。
4. 交通・まちの利便性向上
バス路線の新設やダイヤ改正、駅前の再整備、歩行者優先の道路設計など、日常の移動のしやすさにも国勢調査が関わります。
人口密度や通勤・通学の方向、世帯構成の変化を踏まえて、公共交通の維持・改善やシェアモビリティの導入などが検討されます。
買い物や通院に不便のない生活圏を描くための“地図の背景”として、最新かつ信頼性の高い人口データが使われます。
5. 仕事と産業の見通しづくり
働く人の職業や産業、雇用形態の分布は、地域の強みや課題を映します。
国勢調査は、企業の立地や新規出店、オフィス開設の判断材料となるほか、職業訓練やリスキリングの対象設計にも活用されます。
たとえばIT人材の不足が見込まれる地域で、自治体が民間と連携して研修プログラムを設計するといった取り組みは、国勢調査の分析からスタートします。
6. 公平な行政サービスの配分
国や自治体の予算配分、地域間の財政調整、社会保障に関わる給付・サービスの見込みにおいて、客観的で比較可能な人口データは不可欠です。
国勢調査は、地域の規模や実情に応じた公平な資源配分を可能にし、“どこに住んでも一定の行政サービスを受けられる”という安心の前提を支えています。
7. 民主主義の土台——選挙区の区割り
衆議院小選挙区などの区割りや議席配分の基礎資料には、国勢調査の人口が用いられます。
人口の変化に応じて区割りが見直されることで、一票の価値の偏りを縮小する努力が続けられています。
国勢調査は、選挙の公平性という民主主義の根幹にも関わる重要な役割を担っています。
数字が変える日常——データから生まれる具体的な改善例
たとえば、ある町で単身高齢者が増えていることが国勢調査で明らかになったとします。
自治体はこれを受け、徒歩圏に小型スーパーを誘致し、移動販売のルートを再設計。
さらに、地域包括支援センターの人員配置を見直し、見守り活動を強化しました。
結果として、買い物の不便が改善され、孤立防止の仕組みも機能するようになりました。
こうした“生活の細部に届く改善”の起点に、国勢調査の客観的な数字があるのです。
別の例では、若い世代の転入が多いエリアで保育需要の増加が予測され、保育士の採用支援と施設の増設が前倒しで実施されました。
開園時期が需要のピークに重なり、待機児童の発生を最小限に抑えることができました。
先を見据える計画づくりは、正確なデータがあってはじめて可能になります。
長期の連続性が見えるから、変化を捉えられる
国勢調査の強みは、全国一律の方法で長年にわたり実施されていることです。
数十年スパンで日本の人口構造や就業の姿がどのように変わってきたのか——たとえば、核家族化の進行、女性の就業率の上昇、都市部への人口集中、地方圏での年齢構成の変化など——を統一指標で追うことができます。
過去と現在を同じ“ものさし”で比べられるからこそ、政策の効果検証や次の一手の設計が確かなものになります。
短期の統計やアンケートでは見落としがちな大きな潮流を、国勢調査はしっかりと捉えます。
地域の可能性を引き出す、オープンな資源
国勢調査の結果は、統計表や地図と組み合わせた形などで公開され、誰もが活用できます。
自治体の政策だけでなく、NPOや地域団体の活動計画、商店街の顧客分析、防犯・防災の自主活動など、多様な主体が“共通言語”として使えるのが特長です。
公開されたデータをもとに、新しい移動サービスや地域アプリが生まれたり、空き家対策の重点地区が可視化されたりと、データ活用の裾野は広がっています。
地域の課題を可視化し、共通の土台で議論できること自体が、合意形成の質を高めます。
あなたの一回答が、社会を動かす
国勢調査は、ひとり一人の状況を積み重ねて社会の姿を描き出します。
ひとつの世帯の情報は小さく見えても、集まることで保育所の必要数や病院の体制、交通の利便性、そして公平な選挙の実現にまで影響を与えます。
正確に、漏れなく、あるがままの状況を回答いただくことが、より良い地域の未来につながります。
また、継続して実施されることにより、前回からの変化が明確になります。
変化が大きければ対応を加速し、落ち着いていれば維持や改良に資源を振り向けられます。
社会の舵取りを誤らないために、国勢調査の安定したデータ供給は欠かせません。
データでつながる安心な暮らしへ
少子高齢化、人口減少、働き方の多様化、外国籍住民の増加、気候変動による災害リスクの高まり——社会はめまぐるしく変化しています。
こうした変化のなかで、すべての人に必要なサービスを行き届かせ、誰も取り残さない社会を実現するには、現状を正しく把握し、根拠に基づいて行動することが不可欠です。
国勢調査は、そのための最も基本で、最も広く使われる土台の統計です。
毎回の国勢調査は、次の5年、その先の10年の地域の姿を形づくる貴重な機会でもあります。
暮らしに直結する多くの政策やサービスが、皆さまからの回答をもとに設計され、改善されていきます。
ご協力を通じて、日本の「いま」と「これから」を、ともにより良いものへと育てていきましょう。
調査は誰が対象で、いつ・どのような方法で実施されるの?
調査の対象は誰? ——「日本に住んでいるすべての人」と「すべての世帯」
国勢調査は、日本国内の人口・世帯の姿を正確に把握するため、国内に住んでいるすべての人と、全ての世帯を対象に実施します。
ここでいう「住んでいる」とは、ふだん生活の拠点として寝起きしている場所(常住地)を意味し、国籍は問いません。
生まれたばかりの赤ちゃんから高齢の方まで、また、留学生や就労で滞在している外国籍の方も含みます。
対象とするかどうかの目安は、「日本に3か月以上住んでいる、または住む予定があるかどうか」です。
短期間の観光目的での訪日など、3か月未満の滞在者は対象外です。
一方で、日本国籍であっても、海外に3か月以上滞在し日本に住所を有していない場合は対象外となります。
対象に含まれる主な例
- 日本国内に居住するすべての人(日本国籍・外国籍を問わない)
- 生後まもない乳幼児
- 学生で実家を離れて下宿・寮・一人暮らしをしている人
- 単身赴任や就職で家族と別居している人
- 長期に入院・入所している人(病院や社会福祉施設等にいる場合は、その施設で取りまとめて回答)
- 会社や学校等の寮、寄宿舎、社宅、シェアハウスで暮らしている人
- 自衛隊基地、官舎、寄宿施設等で生活している人
対象外となる主な例
- 観光・短期出張などで3か月未満の短期滞在の人
- 海外で3か月以上生活している人(長期赴任・留学など)
- 日本国内にふだんの住まいを持たず、調査時点において海外に居住している人
- 別荘・セカンドハウスを時々利用しているだけの人(ふだん寝起きしていない場合)
どの住所で回答する? ——「常住地」の考え方
回答は、ふだん主として生活している住居(常住地)で行います。
二拠点居住や引っ越しが重なった場合は、次を目安にしてください。
- 引っ越し直前・直後:基準日(後述)に実際に住んでいた方の住所で回答
- 二つ以上の住まいがある:生活の中心で過ごす時間が長い方の住居で回答
- 単身赴任や下宿の学生:現在暮らしている赴任先・下宿先で回答(実家では回答しない)
- 長期入院・入所中:入院・入所先の施設を通じて回答
いつ実施されるの? ——5年ごと、基準日は10月1日
国勢調査は5年ごとに実施され、調査時点の基準日は10月1日です。
国内の人口・世帯の「ある一時点の姿」を全国で同じ日にそろえるため、基準日が定められています。
たとえば、令和7年(2025年)は実施年に当たり、10月1日時点の状況を回答していただきます。
実施までのおおまかな流れ(標準的なスケジュール)
- 9月上旬〜中旬:調査員または郵便で「調査のお願い」「インターネット回答のアクセス情報」などの書類を配布
- 9月中旬〜:インターネット回答の受付が始まる(24時間いつでも回答可能)
- 10月1日:調査の基準日(この時点の居住状況・就業状況等で回答)
- 10月上旬:紙の調査票での提出期限(郵送または回収)
- 10月上旬〜中旬:未回答世帯への連絡・確認
各地域で配布日程や回収方法に一部違いが出る場合がありますが、基準日(10月1日)に合わせて全国で統一的に実施されます。
どのように実施される? ——3つの回答方法から選べます
できるだけ手軽に、負担なく回答いただけるよう、次の方法をご用意しています。
最も推奨しているのはインターネット回答で、入力ミスの自動チェックやガイダンスがあり、短時間で完了します。
インターネットで回答する
配布された「アクセスID」と「初期パスワード」を用いて専用サイトにアクセスし、案内に沿って入力します。
スマートフォン、タブレット、パソコンのいずれでも利用できます。
- 24時間、都合の良いタイミングで回答可能
- 途中保存ができるため、時間をおいて再開できる
- 入力不備を自動で確認し、スムーズに完了できる
- 多言語表示ややさしい日本語に対応(言語は画面で選択)
完了後は「受付完了」の表示が出ます。
必要に応じて控えを保存してください。
紙の調査票で回答する
配布された調査票に記入し、同封の封筒に入れて郵送するか、地域の案内に従って回収を受けます。
封筒は内容が見えないように密封し、宛先不要・切手不要で投函できる場合があります。
記入は読みやすいペンで行い、数字や選択欄は案内に沿って明確にご記入ください。
調査員によるサポートを受ける
調査員は、市区町村の長が任命し、統計調査員証(身分証)を携行しています。
必要に応じて使い方や回答の流れをご説明します。
対面での回収が不安な場合は、非対面(ポスト投函・郵送)やインターネット回答へ切り替えることも可能です。
不在時には投函で資料をお届けし、連絡先を明記しますので、都合の良い連絡方法でご相談ください。
多言語・アクセシビリティへの配慮
回答サイトや案内資料は、多言語に対応しています(例:英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、やさしい日本語など)。
聴覚・視覚に配慮したサポートやコールセンターも用意されます。
もし日本語での回答が難しい場合は、配布資料に記載の窓口へお問い合わせください。
回答にかかる時間の目安
- 単身世帯:おおむね10分程度
- 2〜3人世帯:10〜15分程度
- 4人以上の世帯:15〜20分程度(世帯員数により前後)
インターネット回答は入力補助があり、比較的短時間で完了します。
場面別の答え方——迷いやすいケースを整理
生活スタイルや居住の状況によって、どこで・どう回答するか迷うことがあります。
代表的なケースの考え方をご紹介します。
引っ越しが基準日前後にあった
- 基準日(10月1日)に住んでいた住所で回答します。
- 住宅の鍵渡しや住民票の異動日ではなく、実際に生活していた場所を基準にしてください。
- 二重に回答しないよう、旧居・新居での重複にご注意ください。
帰省・長期出張などで家を空けている
- 一時的な不在の場合は、ふだん住んでいる自宅の世帯として回答します。
- 不在時はインターネット回答が便利です。必要なアクセス情報は事前に家族で共有しておくとスムーズです。
留学・海外赴任をしている
- 海外での滞在が3か月以上に及ぶ場合は、国内の国勢調査の対象外です。
- 3か月未満の短期出国で、ふだんの住まいが国内にある場合は、国内の世帯として回答します。
学生の一人暮らし・寮・下宿
- 実家ではなく、実際に暮らしている住所(アパート・寮・下宿先)で回答します。
- 同じ建物で複数人が暮らす寮・寄宿舎などは、管理者を通じて取りまとめる方法になることがあります。
単身赴任・別居で働いている
- 赴任先で常日頃生活している場合は、赴任先で回答します。
- 配偶者や家族が元の住居に残る場合、それぞれの居住地で世帯として回答します。
施設に入院・入所している
- 病院や介護・福祉施設、矯正施設などに長期でいる人は、施設側の取りまとめにより回答します。
- 家族は重複回答にならないよう、施設での扱いを確認してください。
調査書類の受け取りから回答まで——手順のイメージ
- 9月ごろ、調査員または郵便で「調査のお願い」「アクセスID等のご案内」「紙の調査票(必要に応じて)」が届く。
- 記載内容(住所表示、世帯名、問い合わせ先)を確認し、なくさないよう保管。
- インターネット回答または紙の調査票のいずれかを選択。
- インターネットならアクセスIDでログインし、案内に沿って入力・送信。紙なら記入後、同封の封筒で郵送、または回収方法に従う。
- 未提出の場合は、調査員やコールセンターから提出方法のご案内があることがあります。
安心して回答いただくためのポイント
- 調査員は必ず「調査員証(身分証)」を携帯しています。不安な場合は提示を求めてください。
- アクセスID・初期パスワードは大切に保管し、第三者に知らせないでください。
- 電話やメールで個人の金融情報や暗証番号を聞き出すことはありません。不審な連絡は、配布物記載の公式窓口で確認してください。
- 提出済みか不明な場合は、世帯内での連携や控えの確認をお願いします(重複提出の心配があるときも、まずは公式窓口にご相談ください)。
なぜ「全員対象」なのか——調査の正確さを支える仕組み
国勢調査は、地域の医療・保育・教育・防災から、交通やまちづくり、選挙区の設定まで、行政のあらゆる計画に直結します。
全員を対象とする「完全調査」であることが、地域ごとの人口構成や世帯の姿を正しく把握する唯一の方法です。
ひとつの世帯・お一人の回答が欠けると、地域の人口把握に偏りが生じ、必要なサービスの見通しにも影響が出ます。
だからこそ、基準日を統一し、全国同時に、どの住まいでも同じ方法で回答できる仕組みを整えています。
スムーズに回答するためのちょっとした工夫
- 前もって家族の就業状況や通学先、年齢などを確認しておくと入力が早く済みます。
- アクセスIDの写真を撮っておく、控えを別に保管するなど、紛失対策を。
- 在宅が難しい世帯は、インターネット回答や郵送提出を活用。
- 集合住宅では投函物の誤配に注意し、必要に応じて管理人・管理会社にも到着状況を確認。
まとめ——基準日をそろえ、方法は選べる
国勢調査は、国内に住むすべての人と世帯が対象で、5年ごと、10月1日を基準日に実施します。
回答方法は、インターネット、紙の調査票、調査員サポートのいずれも可能。
生活の実態に合わせた「常住地」で回答し、引っ越しや不在があっても、ルールに沿って迷わず提出できます。
短時間のご協力が、地域の将来設計に直結します。
配布資料の案内に沿って、期限内の回答をよろしくお願いします。
回答は義務なの?期限や回答方法(オンライン・紙・訪問)はどうなっているの?
回答は義務? —法的根拠と罰則のポイント
国勢調査は、法律(統計法)に基づいて実施される「基幹統計調査」です。
したがって、対象となる世帯には回答義務があります。
あわせて、実態に即した内容を記入する真実回答の義務も定められています。
統計法には、正当な理由なく回答を拒否したり、虚偽の回答をしたり、調査を妨げたりした場合に適用される罰則が規定されています。
内容は要約すると次の通りです。
- 対象世帯には回答の協力が求められ、回答を拒否・妨害・虚偽記入などには罰則(50万円以下の罰金)が設けられています。
- 調査で得た個人情報は厳格に保護され、統計以外の目的(税務、警察、入管、裁判等)に使うことは法律で固く禁じられています。
- 調査に従事する者には守秘義務が課され、違反した場合の罰則も整備されています。
国勢調査は、学校・病院・道路・防災・選挙区など、あらゆる公共サービスの基礎データになります。
世帯の一件一件の回答が、正確で公平な行政の前提となるため、法的な義務として位置づけられているのです。
回答期限の考え方—基準日、受付期間、締切後の対応
国勢調査には、全国で共通の基準日があり、その時点(午前0時)の状況をもとに回答します。
基準日は通常10月1日に設定されます。
受付期間のめやす
具体的なスケジュールは地域の配布物・案内状に記載されますが、おおむね次の流れです。
- オンライン先行期間:9月中旬ごろから基準日直後まで。配布されたログイン情報で、スマホ・PCから回答できます。
- 紙の調査票の提出期間:基準日前後~10月中旬ごろ。調査票を記入し、封入して提出します。
- 最終受付・回収:10月中旬~下旬ごろまで。期日を過ぎた場合も、可能な限り早めに提出してください。
地域により締切日は多少前後します。
詳しい期限は、配布された「調査のお願い」や投函用封筒、またはコールセンター・自治体の案内で必ず確認してください。
期限を過ぎたらどうする?
期限を過ぎても、未提出であればできるだけ早く提出してください。
オンラインは期間延長により受け付けている場合があり、紙も回収が続いていることがあります。
提出方法が分からない、資料を紛失した、といった場合は配布物の連絡先やコールセンターに相談すれば、再発行や回収の調整を案内してもらえます。
基準日の「切り取り方」
回答内容は基準日(10月1日午前0時)時点の事実でそろえます。
たとえば、引っ越しや出生・転出入が基準日前後にあった場合も、どの時点でどこに居住していたかを基準に整理するとスムーズです。
迷うケースはコールセンターに具体的な状況を伝えて確認してください。
3つの回答ルート—オンライン・紙・対面サポートの違い
国勢調査は、どなたでも回答しやすいように複数の方法を用意しています。
いずれの方法を選んでも、提出された内容は同等に扱われます。
スマホ・PCでのオンライン回答
最も推奨されるのがインターネット回答です。
24時間いつでも、スマホ・タブレット・PCからアクセスできます。
多言語対応やアクセシビリティにも配慮されています。
ログイン方法とセキュリティの確認
- 配布物に記載のログインID・アクセスキー(初期パスワード)で専用サイトにサインインします。
- URLは配布物にある正規アドレスや公式QRコードからアクセスしてください。検索結果や広告経由は避け、ドメイン名・鍵マーク(HTTPS)を必ず確認しましょう。
- 電話やSMS、SNSでログイン情報を教えるよう求められても絶対に教えないでください。
入力のコツと保存・修正
- 設問は画面の案内に沿って順番に回答します。迷った設問は「後で見直す」等の機能を活用し、入力途中でも保存できます。
- 世帯員の追加・削除は該当画面で調整できます。基準日時点での構成に合わせてください。
- 送信後に誤りに気づいた場合は、受付期間中にコールセンターや担当者へ連絡すると訂正方法の案内を受けられます。
紙の調査票での提出
紙での回答も選べます。
落ち着いて記入でき、控えを手元に残したい方にも向いています。
記入の注意と封入のしかた
- 記入は読み取りやすいペンで丁寧に。数字やチェック欄は、設問の指示に合わせて記入してください。
- 誤記した場合は、二重線と訂正印の指示がある場合に従うか、新しい調査票の再発行を依頼してください。
- 記入後は同封の封筒に厳封し、案内に従って提出します。封筒には現金やキャッシュカード情報、マイナンバー等は一切同封しません。
回収方法(ポスト・訪問・投函箱)
- 郵便ポスト投函、回収ボックス、担当者による回収など、地域の案内に記載の方法から選びます。
- 在宅時間が合わない場合は、置き配・非対面回収の相談も可能です。
調査員による訪問支援
必要に応じて、調査員のサポートを受けられます。
操作が不安な方や記入が難しい方は遠慮なく相談してください。
本人確認と依頼できる支援内容
- 調査員は顔写真付きの身分証や腕章、配布物を携行しています。提示を求めて確認してください。
- オンラインのログイン方法の案内、紙調査票の記入補助、提出方法の説明などの無料サポートを行います。
費用請求や口座情報要求は一切なし
- 調査に関連して手数料を請求することはありません。
- 口座番号、クレジットカード番号、キャッシュカードや暗証番号、マイナンバー等を求めることは絶対にありません。そのような要求があれば、不審事案として相談してください。
どの方法を選ぶべき? —状況別のおすすめ
忙しい・在宅時間が不規則なら
24時間回答できるオンラインが便利です。
スマホで10〜15分程度が目安。
途中保存すれば、通勤中や休憩時間に少しずつ進められます。
控えを残したい・落ち着いて確認したいなら
紙の調査票で一度下書きしてから清書し、コピーを手元に保管して提出すると安心です。
提出は投函や非対面回収の活用を。
高齢の家族や障害がある方がいるなら
訪問支援や電話相談を活用し、無理のない方法で回答できます。
代理での入力・記入も可能です。
困りごとは、配布物に記載のコールセンターへ。
よくある誤解と注意点
「世帯主でないと回答できない?」
世帯をよく把握している方であれば、世帯主以外でも回答可能です。
内容は世帯全員分を基準日でそろえるよう、家族間で確認してから提出してください。
「匿名で出したい」
国勢調査は世帯ごとに配布されるIDで管理されますが、統計以外に使われることはありません。
記入内容が個人名と結びついた形で外部に出ることは法律で禁止されています。
安心して正確にご回答ください。
「調査票は必ず直接手渡し?」
直接の受け渡しに限りません。
オンライン回答、ポスト投函、回収ボックスなど、対面せずに完結する方法も用意されています。
「インターネットは個人情報が不安」
正規サイトは通信の暗号化やアクセス制御など、セキュリティ対策を施しています。
必ず配布物のURL・QRからアクセスし、HTTPS(鍵マーク)の確認を。
公共施設の無料Wi‑Fi利用時は、個人端末のセキュリティ更新と自動接続設定の見直しも行うと安心です。
困ったときの連絡先・再発行の受け方
オンラインIDを紛失した
配布物の紛失・破棄・未着などがあっても、再発行が可能です。
世帯の住所や氏名などを確認し、本人確認のうえ手続きします。
配布物の連絡先・コールセンターに相談してください。
調査票をなくした・破損した
新しい紙の調査票の配布や、オンラインへの切替え案内を受けられます。
期限が迫っている場合は、まずオンラインでの回答可否を確認するのが迅速です。
迷惑電話や不審な訪問への対処
- 調査を名乗る者からの金銭要求・口座情報要求はすべて不審です。応じないでください。
- 不審に思ったら、配布物記載の窓口に確認し、必要に応じて#9110(警察相談)等へ通報してください。
スムーズに終えるための小さなコツ
- 所要時間の目安:世帯の人数にもよりますが、オンラインで10〜20分、紙で15〜30分程度が一般的です。
- 事前メモ:世帯員の生年月日や就業状況など、聞き取りが必要な事項をメモしてから始めると一度で完了しやすくなります。
- 基準日を意識:回答は「10月1日午前0時時点」の状態で統一。引っ越しや出張などは基準日を軸に整理します。
- オンライン優先期間を活用:初期段階で済ませると、回収のための訪問・連絡を受ける必要がなく、双方にとって効率的です。
まとめ—期限内に、都合の良い方法で確実に
国勢調査は、統計法に基づく回答義務のある調査です。
基準日(通常10月1日)時点の状況で、オンライン・紙・訪問支援のいずれかを選んで期限内の提出をお願いします。
万一、締切を過ぎた場合も、可能な限り早く提出すれば受付されることが多いため、ためらわずに行動してください。
オンラインは手早く安全に、紙は落ち着いて丁寧に、訪問支援は不安を解消しながら——どの方法でも、皆さんの回答はより良い暮らしの設計図につながります。
迷ったら案内状やコールセンターを活用し、確実・安心な回答を完了させましょう。
個人情報とプライバシーはどのように守られ、結果は何に活用されるの?
国勢調査の個人情報保護とデータ活用のしくみ
国勢調査は、日本のすべての人と世帯の実態を把握する、最も基礎的な統計です。
正確な統計をつくるためには、安心してご回答いただけることが何より大切です。
ここでは、個人情報とプライバシーがどのように守られているのか、そして集計された結果が社会のどこで役立っているのかを、仕組みと事例を交えてわかりやすくご説明します。
個人情報とプライバシーを守る基本原則
国勢調査は、統計の作成・公表という明確な目的のもとで実施され、個人の権利利益を守るために、次の原則が徹底されています。
- 統計の目的以外には一切使わない(目的外利用の禁止)
- 個人や世帯が特定される形では公表しない(秘匿・匿名化の徹底)
- 調査に従事するすべての者に秘密保持義務を課す(厳格な守秘の義務化)
- 必要な範囲に限って情報を収集・管理する(最小限・適正管理)
- 安全管理措置を講じ、技術的・組織的に保護する(制度と技術の両輪)
統計法にもとづく厳格な守秘と目的限定
国勢調査は統計法に基づいて実施されます。
調査で得られた情報を統計の作成・公表以外に使うことは法律で禁じられており、税務、社会保障、捜査・取締り、入国管理など、個人の不利益につながる用途に提供されることはありません。
また、調査員や集計業務に従事する者には秘密保持義務が課され、違反には罰則が適用されます。
制度面の歯止めを明確にすることで、目的外の利用や漏えいを許さない仕組みをつくっています。
公表は集計のみ—「個人がわかる情報」は外に出ない
公表されるのは、地域や年齢階級などに区分して集計した統計表や地図だけです。
特定の人や世帯が推測されるおそれがある小さな数値については、非表示や統合、丸めなどの秘匿処理を行い、公表段階で個人が識別されないように加工します。
氏名などの識別情報は、重複排除や確認などの技術的な目的を除き、集計や公表には用いません。
現場での安全対策—紙とオンラインの両面
紙の調査票の取り扱いはこう守られます
紙の調査票で回答される場合も、複数の安全策で守られています。
- 配布時の確認:調査員は顔写真付きの調査員証を携帯し、身分を明らかにして配布します。
- 封入と回収:記入後は封筒に封をして提出します。ポストへの投函、回収箱への投入、封緘したままの手渡しなど、内容が第三者の目に触れない方法で回収します。
- 閲覧防止:調査員が回答内容を開封して確認することはありません。封緘された状態のまま統計作業の拠点へ送付されます。
- 保管・廃棄:調査票は、入退室管理が施された場所で厳重に保管され、統計作成に必要な処理を終えた後は適切な手順で廃棄されます。
調査員の誓約と行動基準
調査員には、研修の受講と秘密保持の誓約が義務付けられています。
調査に関連して、現金・商品券・口座情報などを求めることは一切ありません。
万一不審に感じる点があれば、調査書類に記載のコールセンターや自治体窓口へご連絡ください。
オンライン回答のセキュリティ
インターネットでの回答は、通信の暗号化などの技術的対策で守られています。
- 暗号化通信:回答内容は暗号化された通信経路で送信されます。
- アクセス情報:配布された案内書に記載のログイン情報でのみアクセス可能です。
- タイムアウト・再ログイン:一定時間操作がない場合は自動的にログアウトし、第三者によるのぞき見を防ぎます。
- URLの確認:正規のURLからのみ回答を受け付けます。案内書に記載のアドレスをご確認ください。
共有端末でのちょっとした注意
- 入力後は必ずログアウトする
- ブラウザの自動保存機能をオフにするか、終了時に履歴・キャッシュを削除する
- 不特定多数が使う端末では回答しない
よくある心配への答え
氏名を書くのはなぜ?
世帯員の氏名は、回答の重複や記載内容の確認を適切に行うために用います。
氏名そのものを集計したり、公表したりすることはありません。
統計の作成に必要な工程を終えた後、氏名などの識別性が高い情報は、統計的な利活用の観点からも適切に管理・分離されます。
他の制度や手続きに使われないの?
使われません。
統計法により、国勢調査の情報は統計の作成・公表以外に利用できません。
税務調査、社会保障の審査、警察の捜査、入国管理など、個人の不利益につながる用途に提供されることはありません。
マイナンバーとは関係がある?
国勢調査でマイナンバー(個人番号)を尋ねることはありません。
調査票やオンライン画面で、マイナンバーの入力・提示を求めることもありません。
外部に“元データ”が出ることは?
個人や世帯を識別できる「個票」の形で外部に提供することはありません。
研究・政策評価など高度な分析に用いる場合でも、本人が特定されないように加工したデータを、審査と管理の行き届いた環境でのみ利用できる仕組みにしています。
集計結果はどこで見られ、どう役立つのか
集計結果は、政府統計のポータルサイト(e-Stat)などで順次公開されます。
人口や世帯、就業、通勤・通学など、多様なテーマの統計表や地図データを無料で閲覧・ダウンロードできます。
公開データは、社会のさまざまな場面で活用されています。
身近なサービスの質を上げる活用例
- 医療・救急の体制整備:時間帯・地域別の人口構成や就業状況をもとに、救急搬送の需要見込みや夜間医療の体制を調整。
- 保育・学童の受け皿確保:年齢階級別の子どもの人数や世帯の働き方の傾向から、保育所・学童の設置や職員配置を計画。
- 防災・避難所運営:地域ごとの世帯人数や高齢化の度合いに応じて、備蓄量や避難所の受け入れ体制を見積もり、訓練計画にも反映。
- 公共交通と道路計画:通勤・通学パターンや居住分布を踏まえ、バス路線の再編、ダイヤ調整、歩道整備の優先順位付けを実施。
- 住まいとまちづくり:世帯の規模や構成の変化を基に、住戸タイプの需要見通し、公園・図書館など生活インフラの配置を検討。
- 地域産業の支援:産業別の就業構造や人材の偏在を把握し、雇用対策や創業支援、企業誘致の戦略作りに活用。
民間の創意工夫を後押しする使い方
- 商圏分析と出店計画:来店が見込まれる年齢層や世帯構成を見極め、店舗の立地や品揃えを最適化。
- 物流・宅配の効率化:住宅密集地や単身世帯の多い地域を把握し、配達ルートや車両配備を改善。
- 不動産・住宅サービス:地域の家族構成や居住年数などの傾向を踏まえ、住み替え提案や住宅リフォームの需要を分析。
- 観光・イベント運営:地域の人口動態と交通の結節点を重ね、混雑緩和や多言語案内の配置を工夫。
- 教育・人材育成:地域の産業構造と若年人口の動向から、職業訓練やリスキリングの重点分野を決定。
研究・政策評価での高度な分析
大学や研究機関、行政機関では、国勢調査の集計データを他の公的統計と組み合わせ、少子高齢化、労働市場の変化、都市と地方の人口移動、生活の多様化など、社会課題の構造を丁寧に解き明かしています。
より詳細な分析が必要な場合は、本人が特定されないよう加工されたデータを、審査・管理の行き届いた環境で利用する仕組みを用い、個人情報保護と学術的価値の両立を図っています。
統計づくりの舞台裏—データはこうして安全に加工される
集まった回答は、次の流れで丁寧に処理されます。
- 受け付けと点検:重複や記入漏れの確認、機械判読のための整形を実施。
- 符号化・編集:回答を統計的に扱える形に変換し、誤記や不整合を点検。
- 匿名化・秘匿の準備:個人を識別できる情報を分離し、集計時の秘匿基準を設定。
- 集計と検証:地域別・年齢別など多様な切り口で集計し、外れ値や矛盾をチェック。
- 公開と説明:統計表・地図・解説資料を整え、再現可能性のある形で公開。
小さな地域でも個人が見えない工夫
町丁・字といった小地域の統計は、きめ細かな計画づくりに有用ですが、個人が推測されないよう特に慎重な配慮を行います。
人数が極端に少ない属性や、特定の世帯だけが該当するような数値は、非表示や地域の統合、丸め処理などを組み合わせて秘匿します。
これにより、利便性とプライバシー保護の両立を図ります。
安心して参加するためのワンポイント
- 案内書に記載のURL・連絡先を確認する
- 調査員証を必ず確認する(不審な請求や依頼には応じない)
- オンライン回答は暗号化通信の表示(https)を確認する
- 紙の調査票は封筒に封をして提出する
- 回答の控えが必要なら、オンラインの確認画面や紙の記入前のメモを保管する
あなたの一回答が、安心で便利な社会をつくる
国勢調査は、みなさまの協力で初めて成り立つ公共の知恵です。
回答内容は、法律と技術の両面から厳重に守られ、個人がわかる形で外に出ることはありません。
一方で、集計された結果は、医療や教育、防災、移動、子育て支援、働き方など、暮らしの基盤を支える数え切れない施策に生かされます。
安心してご回答いただくことが、より安全で便利な社会への最初の一歩です。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
正しい国勢調査を見分けるには?公式連絡や調査員の確認方法・詐欺の見抜き方は?
本物の国勢調査を見極めるポイント—公式連絡の特徴、調査員の確認、詐欺対策
国勢調査をかたる不審な連絡や訪問は、毎回の実施期に増える傾向があります。
ここでは、公式な案内・正規の調査員を確実に見分ける方法、オンライン回答を装う偽サイトの見抜き方、万一の時の連絡や対処までを、具体的なチェックポイントで整理します。
公式な案内・書類の見方
まず「本物」はどのように届くのか、共通する特徴を押さえておきましょう。
- 差出人の表示
- 市区町村名(区役所・市役所等)や都道府県名、または総務省統計局のいずれかが明記されます。
- ロゴやマークだけでなく、公的機関名がはっきり記載されていることを確認してください。
- 書類の内容
- 調査の趣旨・回答方法(インターネット/紙)・回答期間・問い合わせ窓口が、同一の封入物に整理されています。
- インターネット回答用のログイン情報(ID等)は、専用の案内に印字され、個人の金融情報等は一切求めません。
- 連絡先の確認
- 問い合わせ番号は市区町村の代表番号や、自治体サイトに掲載の専用窓口と一致します。
- 封筒やチラシのQRコードからアクセスする場合も、開いた先のURLが公的ドメイン(例:go.jp、lg.jp など)であることを必ず確認してください。
不審点があるときは、封入物の電話番号ではなく、市区町村公式サイトに掲載の連絡先へ自分で検索して照会するのが安全です。
調査員が訪ねてきたときのチェックリスト
提示される身分証の確認
- 顔写真付きの「調査員証」を必ず携帯・提示します。氏名、番号、発行元(市区町村等)が読み取れるか確認してください。
- 腕章や識別用のネックストラップ等を着用しています(地域により形状は異なります)。
- 名乗り方が丁寧で、所属と目的(国勢調査)が明確です。
配布物・携行物の確認
- 「インターネット回答のご案内」「紙の調査票(必要に応じて)」など、公式の説明がセットで渡されます。
- 現金、寄附、商品購入、口座情報の提供などを求めることは一切ありません。
- ログインIDや一時パスワード等を「預かる」「写真に撮る」ことはありません。
訪問時のふるまいと禁じられている行為
- 原則として住居内への立ち入りは求めません。居室への入室依頼や長時間の滞在を求めるのは不自然です。
- 調査票の未封入状態での受領を強要しません。記入済みの紙調査票は封筒に入れ、封緘して提出します。
- 威圧的な督促、罰則を口実とした脅し、夜遅い時間帯の執拗な訪問は正規の対応ではありません。
不在時の対応
- 不在票(連絡票)が投函される場合があります。そこに書かれた番号を鵜呑みにせず、自治体公式サイトで連絡先を確認したうえで折り返してください。
- マンション管理人や第三者に、回答内容やログイン情報を託すことは避けてください。
インターネット回答を装う偽サイトへの対策
正しいアクセスの手順
- 公式サイトへは「総務省統計局(stat.go.jp)」や居住地の市区町村公式サイトからリンクで辿るのが最も確実です。
- DMやSNSのメッセージ、検索広告のリンクは使わず、自分でブックマークした公式ページからアクセスしてください。
URLとセキュリティの確認ポイント
- URLは必ず https で始まり、ドメインは「go.jp」「lg.jp」などの公的ドメインです。似せた綴り(例:go-jp、gov-jp、.comや.info)は要注意です。
- ブラウザの鍵マーク(証明書情報)を開き、運営主体が公的機関であることを確認します。
入力を求められない情報
- クレジットカード番号、銀行口座や暗証番号、寄附や決済の要求は100%偽サイトです。
- 運転免許証や保険証、マイナンバーカードの画像アップロードは不要です。求められた時点で離脱してください。
典型的な手口と即断ポイント
- 手数料・寄附・商品購入を求める
- 国勢調査に費用負担はありません。少額でも金銭の要求=詐欺です。
- 「回答でポイント進呈」「抽選」などの誘引
- 見返りを提示して回答を促すことはありません。リンク先に誘導する狙いです。
- マイナンバーや口座情報、暗証番号の聴取
- 国勢調査でこれらを聞くことはありません。即座に中断してください。
- 外部アプリのインストールや不審なQRコードの読み取り要求
- 公式案内のみ利用し、第三者が提示するアプリやQRは使わないでください。
- 「代行入力します」とID・パスワードの預かり提案
- 第三者による無断代行は認められません。ログイン情報は共有禁止です。
- 回答内容の撮影・複写
- 調査票や画面を撮影・保管することはありません。拒否してください。
- 深夜・早朝の訪問、繰り返しの強い圧力
- 節度ある時間帯での訪問が原則です。恐怖心を煽る言動は正規ではありません。
- 電話・SMSでの即時回答強要
- その場で個人情報を口頭で答える必要はありません。正規の方法(オンライン/紙)で回答してください。
紙の調査票を安全に扱うコツ
- 記入後は封筒に入れてしっかり封をします。未封入のまま手渡さないでください。
- 調査票は折り目や破損を避け、第三者から見えない場所で保管します。
- ポスト投函や回収箱利用の際は、設置場所が公式に案内されたものか確認してください。
- 不要になった控え等は個人情報が判読されないよう適切に破棄してください。
「怪しい」と感じたら—安全第一の行動手順
- やり取りをその場で中断し、個人情報や金銭を渡さない。
- 調査員証の番号・氏名・所属を控え、自治体の公表窓口に直接照会する(自分で検索して連絡)。
- 封筒・名刺・URL・電話番号・メッセージのスクリーンショットなど証跡を保存する。
- 悪質な勧誘や脅しがある場合は、ためらわず110番通報。
- 居住する建物の管理者・家族とも情報を共有し、同様の被害を防ぐ。
住まいの状況に応じた注意点
不在が多い・在宅時間が不規則な場合
- オンライン回答を早めに済ませると、訪問や督促の対象から外れやすくなります。
- 不在票が入っても、記載番号にすぐ連絡せず、自治体公式サイトの窓口経由で連絡を。
高齢者のみの世帯
- 家族がいる場合、公式書類の保管場所や回答方法を事前に共有しておくと安心です。
- 突然の訪問や電話に対応しない方針を決め、必ず折り返しは公的窓口へ。
学生・寮・下宿
- 管理者や同居人を介した回答やログイン情報の共有は避け、個々に正規の方法で回答してください。
- 配布物は寮の掲示と併せて本人に確実に渡るよう、居住先のルールを確認しましょう。
オートロック・集合住宅
- インターホン越しに来訪者の所属と目的、調査員証の提示可否を確認。無理に解錠する必要はありません。
- 管理会社・管理人と、正規の投函方法や回収箱の設置計画を事前に共有すると安全です。
ワンチェックで安心—本物かどうかの合言葉
- お金を求めない・渡さない
- マイナンバー・口座・暗証番号は絶対に答えない
- IDやパスワードは誰にも見せない・預けない
- URLは「https://」かつ「go.jp / lg.jp」を確認
- 身分証は写真・発行元・番号まで確認
- 不審ならその場で中断し、公的窓口に自分で確認
地域でできる見守りと周知
- 自治体掲示板や回覧で、国勢調査の正しい回答方法と詐欺注意を周知する。
- マンション・自治会は、公式以外の回収箱設置や無断の戸別訪問を許可しないルールを徹底する。
- 迷ったら一人で抱え込まず、近隣や管理者に相談できる体制を作る。
安心して回答するために
正規の国勢調査は、わかりやすい書類、丁寧な説明、そして「金銭・口座情報を求めない」という明確な線引きで見分けられます。
訪問者は身分証を提示し、住居内への立ち入りや未封入の回収、執拗な督促などは行いません。
オンライン回答は公的ドメインとhttpsを確認し、ID・パスワードの管理を徹底してください。
少しでも不審に感じたら、その場でやり取りを止め、自治体の公式窓口に確認を。
緊急時は警察へ通報してください。
皆さま一人ひとりの適切な対応が、地域全体の安心と、確かな統計づくりにつながります。
最後に
国勢調査は、1920年開始・5年ごと実施の日本最大の統計で、10月1日現在の全ての人と世帯を国籍問わず把握。
基幹統計として、災害対策、子育て・教育、医療・介護、交通、雇用・産業、予算配分など暮らしの計画と政策の基盤に。
地域間・時系列比較ができ、企業・研究や地域活動にも活用され、公平な行政サービスを支えます。


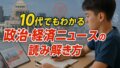

コメント